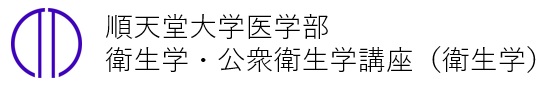英文表記 Department of Epidemiology and Enivironmental Health が表すとおり、当講座は、疫学(Epidemiology)と環境医学(Environmental Health)を中心とした教育・研究を行っています。教育に関しては、医学部ならびに看護学部における衛生学、社会医学、疫学等の講義と実習を担当しています。研究に関しては、環境因子(心理社会因子を含む)が健康に及ぼす影響の疫学研究、有害金属をはじめとする微量元素の生体影響とそのメカニズムなどについて研究しています。国内外の他大学や研究機関の多くの方々とともに研究を進めています。
疫学

疫学研究は統計学の理論を応用し、集団の特性や状況を数字で表して、そこに潜む規則性や傾向性を明らかにし様々な推論をします。山本俊一(1983)によれば「人間集団の健康事象の分布に関する法則性を見出す科学」と定義されています。
疫学は、衛生学・公衆衛生学の重要な手法であり、感染症や慢性疾患などの疾患の発生、進行、および終了にいたるまでのいずれのプロセスにおいても研究対象となります。臨床医学では個々の患者を対象としますが、疫学を中心としたあ社会医学では特定の集団またはコミュニティ全体を対象にします。
疫学の手法には、記述疫学と分析疫学の2つの主要なカテゴリがあります。分析疫学では、疾患のパターンを詳細に調査し、リスクファクターや保護因子を特定します。これには、横断研究、患者・対照研究、コホート研究などが含まれます。さらに介入研究では、ある介入が疾患のリスクにどのように影響するかをテストします。これには、ランダム化比較試験(RCT)が主に用いられます。
環境医学

環境因子(物理的要因、化学的要因、生物的要因および社会的要因)が生体に及ぼす影響を明らかにし、疾
病の予防や治療に役立てます。当講座では特に微量元素 の生体影響について研究しています。
微量元素は、生命維持のために不可欠な栄養素であり、酵素やホルモンの活性化、免疫機能の維持、骨や血液の形成など、生体内で多岐にわたる機能を果たします。そのため、欠乏すると成長障害や免疫機能低下などの問題が生じる可能性があります。一方で、一部の元素については適切な量を超えて摂取すると、悪い健康影響すなわち毒性を示すことがあります。
微量元素分野の環境医学では、食品、水、土壌などからの微量元素のヒトへの曝露量を評価し、その影響を解析することが含まれます。また、微量元素の欠乏や過剰によって引き起こされる可能性のある疾患のメカニズムを明らかにし、それらを予防または治療するための知見を得ています。
アクセス
〒113-8421 東京都文京区本郷2-1-1 順天堂大学 7号館7階北 TEL:03-5802-1047
JR線「御茶ノ水」駅下車(御茶ノ水口) ・・・・・・・・・・・徒歩7分
東京メトロ(丸ノ内線)「御茶ノ水」駅下車 ・・・・・・・・・徒歩7分
東京メトロ(千代田線)「新御茶ノ水」駅下車(B1出口)・・・徒歩9分


教育の目標
本講座では他の社会医学系講座と協力しながら、社会生活、労働および環境が人々の健康に与える影響について、学生の皆さんが医療人の立場から科学的に評価する手法と対応について習得してもらうことを目標としています。私たちが提供する講義や実習は、この学問分野の入り口にすぎません。学生の皆さんには、この講義を道標とし、自らさらに学び進めていただくことを期待します。大学院においては、ご自分のテーマに従って疫学的手法あるいは環境医学的評価を実践する中で、研究者としての自己を確立していただけるよう積極的に助力します。

研究の目標
当講座では、疫学・環境医学分野の研究を並行して行っています。 人間集団を対象とする疫学研究を中心に学際的、国際的研究を、学内他講座、学外諸機関と共同で研究を進めています。現在行っている主なテーマは以下の通りです。
- 妊婦の環境因子暴露とその胎児影響
- 職域におけるメンタルヘルスの評価と対策
- 精神疾患の早期介入における地域資源の活用
- 発達障害のリスクファクターの疫学
- 微量元素の生体影響とそのメカニズム
- その他